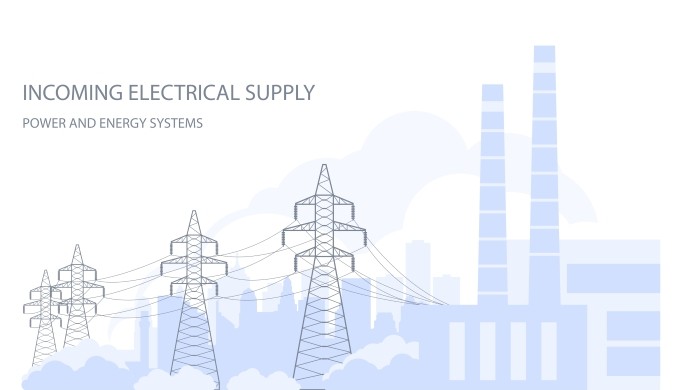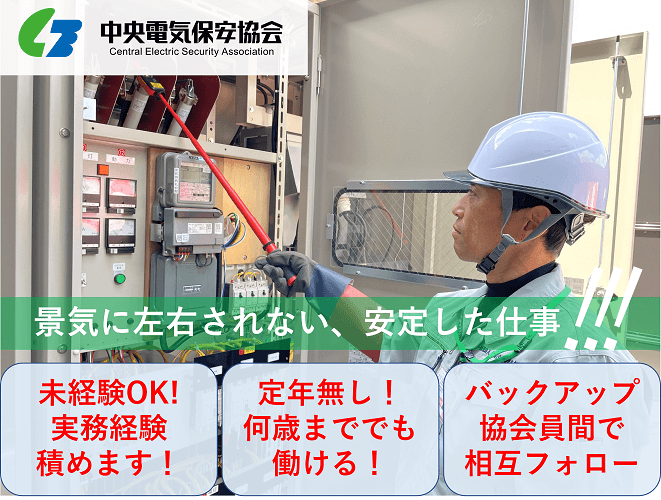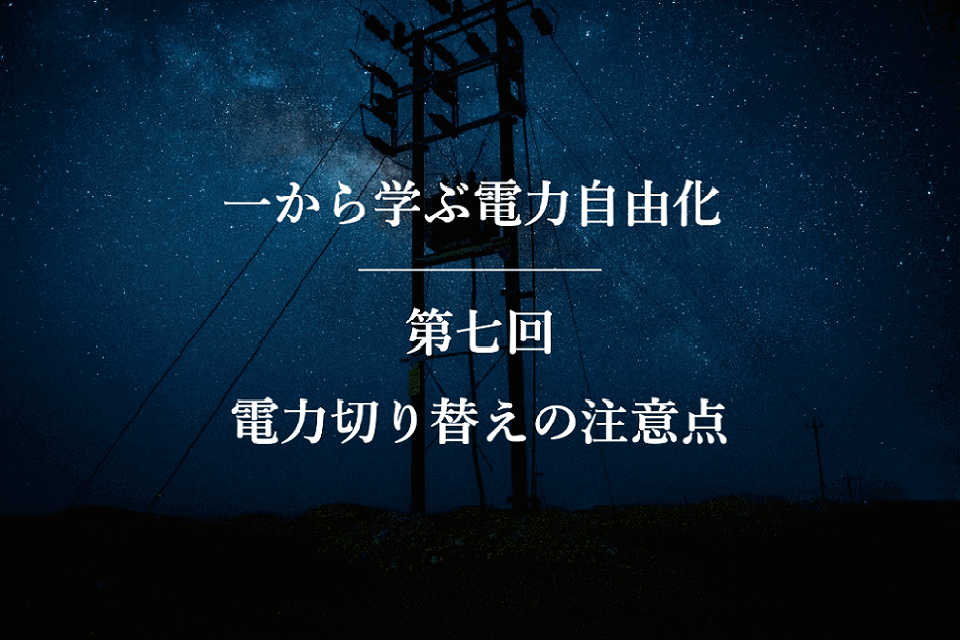電力の安定供給を促すため、新電力を含む小売電気事業者に電力の事前確保を義務とする制度案が7月4日の経済産業省資源エネルギー庁ワーキンググループで提示されました。
まだ決定した訳ではありませんが、どういった背景で提示された案なのか、これが実現するとどんな影響があるかをお伝えします。
背景
2022年のウクライナ侵略を契機に燃料価格が上昇。電力のスポット価格が高騰したことで、小売事業者は顧客に電力を売れば売るほど赤字になる「逆ざや」に直面しました。これによって電力契約の受付を停止する新電力が相次ぎ、契約が出来ずに「電力難民」となった企業の多くが最終保障供給を使わざるをえない状況に陥りました。
現在は小売事業者に調達についての具体的な義務がなく、こういった課題が顕在化した今、対策として、電力供給の3年前には想定需要の5割を確保、電力供給の1年前には7割を確保することを義務付けようという案が提示されました。
影響
この事前確保義務化が実施された場合、先々の電力調達を行なうだけの財務基盤がない中小零細の小売業者は淘汰され、統廃合が進むと考えられます。
ひるがえって、発電事業者にとっては中長期の電力需要がわかるようになれば、計画的に燃料調達を行ないやすくなり、新たな発電設備への投資が促されるという側面もあります。
スポット市場連動型の料金プランを売りにしている事業者は、先々の仕入れを行なうことになる都合上、供給時と仕入時のタイムラグが発生するため、方針転換を迫られることもあるでしょう。
こういった影響を受ける電力会社の顧客として契約をしている方は、何らかの形で契約の変更を行なわなければならなくなるものと思われます。
義務化の是非
まだ検討中の案ということもあり、その是非を問うには早すぎるとは思いますが、制度の目的としては電力の安定供給と市場の健全化を目指すものであり、実際に電力難民となって被害を受けた企業があるなかで、その対策を行なうというのは至極まっとうな流れかと思います。
これを検討していく中で、コスト負担の増加や小規模事業者への影響をどう抑えるか?事業者のサービス設計や自由な競争が損なわれないか?という課題をどう解決するかによって今後の評価も変わっていくでしょう。
変わる制度の中でも変わらず支える
何か問題が起これば、それに対応するために制度や法が変わっていくのは当然のこと。スターメンテナンスサポートでもそれは同じことですが、「お客様にとっての最善を提供する」という方針は変わることはありません。
制度の変更によって多くの企業が方針の変更を迫られ、契約を見直さなければならないという時、私たちは単なる電力会社の代理店としてみなさんに御紹介をするということはいたしません。
みなさんのエージェント(代理人)として、「お客様にとって最も利益になる最適解は何なのか」を最優先にしてご提案いたします。
▶お問い合わせはこちら
参考
第2回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ|経済産業省